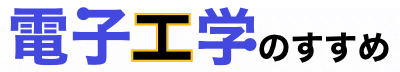勉強した成果が出る!電子工学を独学で始める方法を解説
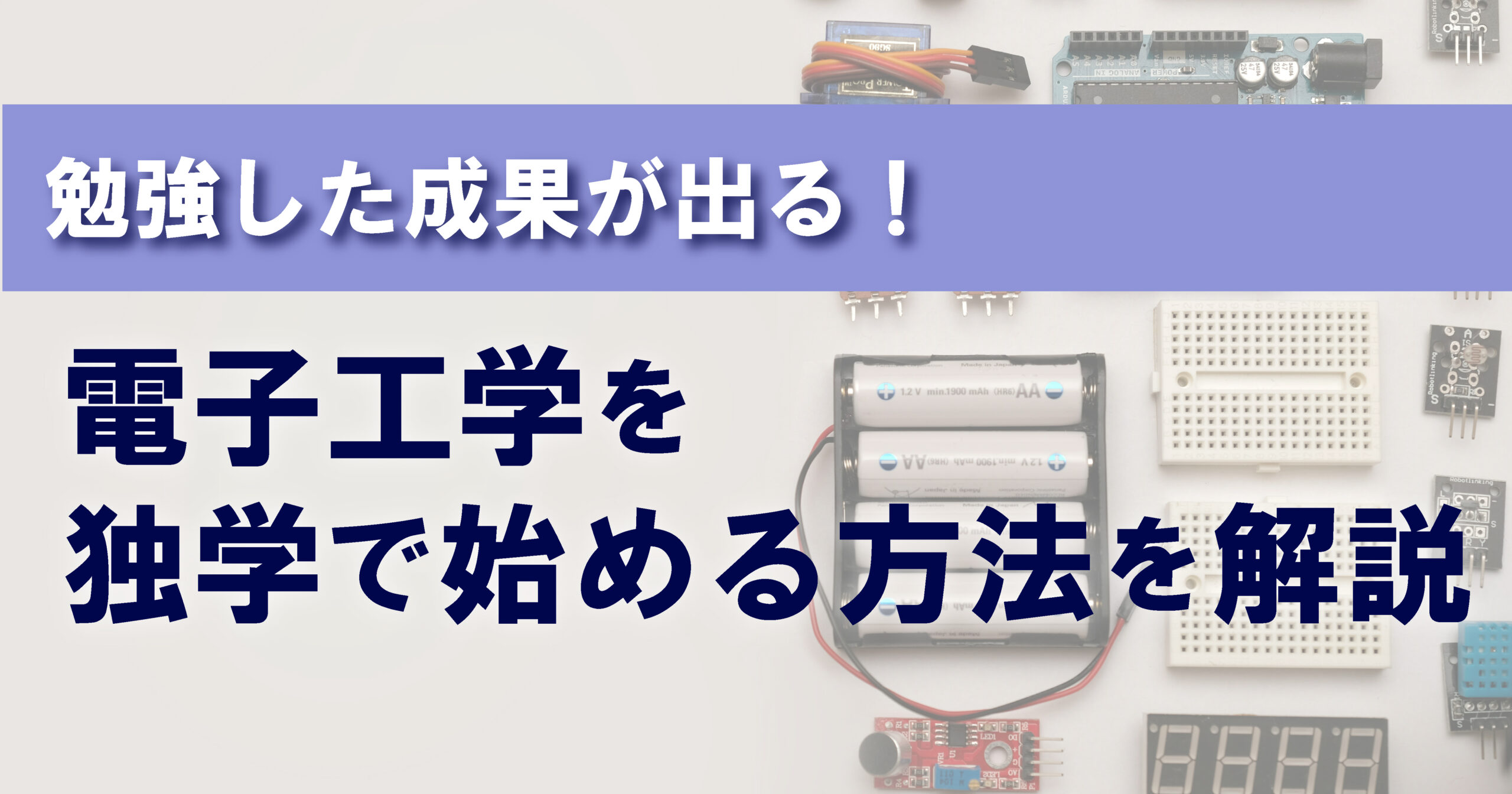
電子工学は現代社会の基盤を支える重要な分野であり、独学でも学習できます。
電子工学の知識は、家電製品から通信システムや医療機器、自動車産業や航空宇宙技術まで幅広い分野で使われている分野です。
特に、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)の発展に伴い、電子工学の重要性はさらに高まっています。
そこで、本記事では、電子工学を独学で勉強する方法を紹介します。
この記事でわかること
- 電子工学を独学する際の難易度
- 電子工学の独学に活用できる資料
- 電子工学を深く理解するための情報
- 電子工学を独学で継続的に学習し続ける方法
電気工学の独学は、決して難しくありません。
しかし、学習範囲が広いため、効率的に学習できるようにポイントを押さえて進めていきましょう。
電子工学の独学を始める前に知っておくべき重要な情報を紹介

独学を始める前に、その難易度と必要な基礎知識についての理解が重要です。
電子工学を独学で学習する際の難易度は、個人の背景や目標によって異なりますが、一般的に中程度から高めになります。
電子工学の基礎知識
- オームの法則
- キルヒホッフの法則
- 抵抗
- コンデンサ
- インダクタ
- トランジスタ
- ダイオード
その中でも、基礎的な数学(特に微積分と線形代数)と物理学の知識が必要です。
特に、電磁気学の基本概念を理解するのは、電子回路の動作原理を把握するうえで非常に重要になります。
さらに、電気回路の基本原理や電子部品における特性の理解も不可欠です。
基本原理としては基本法則や受動素子の特性、能動素子の動作が電子工学の基礎となります。
電子工学を独学で学習する基礎知識について詳しく説明
独学で学習する際のポイントは、段階的に学習を進める点です。
基礎から応用へと順を追って学んでいくにつれ、複雑な概念も円滑にしていきます。
最初は直流回路の解析から始め、次に交流回路やアナログ回路、デジタル回路へと進んでいくと体系的に知識を積み上げられます。
電子工学における学びの中では、過去の情報はもちろん、最新の技術動向も重要です。
というのも、電子工学は急速に進化する分野であるため、常に新しい情報をキャッチアップする姿勢が求められます。
例えば、5G通信技術や量子コンピューティングなどの最先端の技術については、今後スタンダードな知識になりうる分野です。
電子工学に必要な理論と実践を解説
電子工学では、理論と実践のバランスが求められます。
というのも、理論だけでは実際に電子工学で作った制作物が動かない、というケースが珍しくないからです。
そのため、実際に回路を組み立てるケースや回路シミュレーションの実施で理論の理解が深まります。
特に、ブレッドボードを使用した簡単な回路実験は、理論を実践的に確認する上で非常に有効です。
電子工学を独学で学ぶための効果的な教材を紹介

電子工学を独学で学習する際、最初に考えないといけない部分は、適切な教材選びです。
初心者向けの入門書籍としては、「はじめての◯◯」と記載されている書籍があります。
「はじめての◯◯」では中学、高校で学んだ電子関連の復習ができるため、独学の第一歩としておすすめしたい教材です。
「はじめての◯◯」
はじめてシリーズは図解が多く、専門書では難しい部分の半導体素子の基本から回路の動作原理まで、図を多用して分かりやすく解説しています。
加えてマンガなどで紹介されている電子工学書は、視覚的に分かりやすく整理された教材です。
導入部分としてはじめての◯◯やマンガ書籍を理解した後は、少しずつ難しい書籍を使って勉強します。
具体的には大学レベルの教科書がおすすめで、深い部分の理論や背景はもちろん、実践的な内容までカバーしています。
電子工学のオンラインコースや動画教材の特徴を解説
最近では、オンラインコースや動画教材も効果的な学習方法です。
UdemyやCoursera、edXなどのプラットフォームでは、世界中の大学や専門家が提供する電子工学関連のコースを受講できます。
例えばUdemyでは、初心者向けの入門コースから実践的なコース、人気コースなど電気工学と電子工学の講義を視聴できます。
オンラインコース
プラットフォームによって有料、無料は異なるものの、基礎から応用まで幅広いトピックをカバーしているのが魅力です。
YouTubeなどの一般的な動画プラットフォームでも、質の高い電子工学の教育コンテンツが公開されています。
公開されている内容はさまざまですが、実践的な電子工作や回路設計のテクニックが学習できます。
シミュレーションソフトを活用した効果的な学習方法を説明
シミュレーションソフトを活用した学習も、電子工学を実践で学べる手段の一つです。
回路シミュレーションソフトを活用した場合、実際の部品を用意せずに回路の動作が確認できます。
回路シミュレーションソフト
ある程度理論が理解できたうえでシミュレーションソフトを活用すると、電子工学に対する理解が深まります。
シミュレーションソフトで電子回路が簡単に作成できるうえ、わずか数秒から数十秒でシミュレーションの実行が可能です。
学習者は短時間で多くの実験をおこない、さまざまな条件下における回路の挙動を観察できます。
シミュレーションソフトは実際の回路設計の現場でも役立つツールのため、勉強しながら使いこなしておきましょう。
プログラミングや技術フォーラムも独学に有効
電子工学には、マイコンやFPGAの制御やデータ解析など、電子工学の多くの分野でプログラミングスキルが求められるケースもあります。
そのため、C言語やPythonのようなプログラミング言語における基礎の学習もおすすめです。
Python
特に、Pythonは科学技術計算やデータ可視化に強みがあり、電子工学の実験データ解析や回路シミュレーションの結果処理などに広く使用されています。
オンラインの技術フォーラムやQ&Aサイトも、独学では強力な味方になります。
英語版が多いものの、多くのサイトは無料で利用が可能です。
そのため、勉強中に発生した疑問の質問や、ほかの学習者や専門家の投稿を参考にできます。
技術フォーラムやQ&Aサイトは、実践的なアドバイスが得られる点に加え、最新の技術トレンドの情報収集にも役立ちます。
電子工作と回路設計を通じて実践的に電子工学を学ぶ方法を解説

電子工学の理解を深めるには、実際に手を動かした学習が必要不可欠です。
その中でも、初心者向けの電子工作キットでは、基本的な回路の組み立て方や電子部品の扱い方を学習できます。
例えば、LEDを点灯させる簡単な回路から理論を確認し、徐々に複雑な回路へと挑戦するなどです。
Arduino
電子プロトタイピングプラットフォームのArduinoは、スターターキットを用いてプログラミングと電子工作を同時に学習できる優れた教材になります。
実際に設計した回路を製作した後の動作確認で、より実践的な知識とスキルを身につけられます。
基本的な電子回路とブレッドボードやテスターの活用方法と利点を紹介
基本的な電子回路を組み立てるステップとしては、最初に回路図の読み方を学びます。
回路図は電子回路の設計図であり、各部品の接続関係や回路の機能を表現しています。
回路図を正確に読み取る能力は、電子工学において非常に重要なスキルです。
次に、ブレッドボードを使用して実際に回路を組み立てます。
ブレッドボードは、はんだ付けなしで簡単に回路を組み立てられる便利な回路基板です。
実際に回路を組み立てた後は、テスターを使って電圧や電流を測定し回路の動作を確認します。
テスターの使用方法の習得は、回路のトラブルシューティングや性能評価のスキルが身につきます。
例えば、トランジスタを使用した回路やオペアンプを用いた演算回路など基本的な回路を自分で組み上げる体験が、電子回路の理解をより深めます。
むしろ失敗を恐れずに、さまざまな回路の組み立てた経験によって、電子工学を体感的に理解できるようになります。
自作の電子回路作成で実践スキルを飛躍的に高められる
身の回りの課題を解決するような電子機器の製作に自作で挑戦するのは、電子工学のスキルを高める方法としておすすめです。
例えば、光センサーを利用した自動点灯装置など、実用的な回路作成を通じて学習意欲が高められます。
自作の電子回路では、基本的な電子回路の理論はもちろん、センサーからのデータ取得など電子工学のさまざまな側面を総合的に学習できます。
一連のプロセスの実践により、実際の製品開発に近い形で電子工学のスキルを磨けます。
特にデバッグのプロセスは非常に重要で、問題の原因を論理的に追及し解決策を見出す能力を養えます。
自作の電子回路作成で作成に迷った場合は、オープンソースのハードウェアプロジェクトへの参加がおすすめです。
オープンソースのハードウェアプロジェクト
GitHubなどの有名なプラットフォームでは多くのオープンソースが公開されており、実践的なスキルを磨くとともに、コミュニティとの交流を深められます。
最近では、自作の電子回路を作成した成果をブログやSNSなどプラットフォームの共有によって、フィードバックや同じ興味を持つ人々と交流できます。
SNSなどの自分からの発信やフィードバックによって、知識の整理や新たな発見につながる点がポイントです。
加えて、自身のモチベーションの維持により学習理解度が高くなります。
AuduinoやRaspberry Piを活用して電子工学をより深く理解しよう

電子工学の基礎を学んだ後は、次のステップとしてArduinoやRaspberry Piなどのプラットフォームを使用した学習があります。
ArduinoやRaspberry Piなどのプラットフォームは、比較的低コストで高度な電子制御やIoTプロジェクトを実現できます。
そのため、独学者にとって理想的な学習ツールです。
Arduinoはマイコンボードの一種で、オープンソースプラットフォームになります。
Arduinoはシンプルな構造ではんだ付けが不要、プログラミングの知識がなくても始められるプラットフォームです。
具体的にはLEDを点灯させる、センサーからの状態収集、モーターの制御など基本的な電子制御を学習するのに適しています。
Raspberry Piは小型のコンピュータで電子工学は当然として、高度なプログラミングやネットワーク通信に加えて画像処理などの学習が可能です。
Raspberry PiにはCPUやコネクタ、入出力インタフェースを備えています。
さらに、OSが搭載されており、LinuxベースのOSが利用できる点もポイントです。
そのため、電子工学はもちろん、Linuxにおける基本の操作やウェブサーバーに加えてファイルサーバーなどの構築が学習できます。
電子回路は複合的に使われる事象が増えており、センサーからのデータ収集やオートメーション化に加えてネットワーク通信など実践的なスキルを身につけられます。
さらに、利用者が多く、豊富なライブラリやコミュニティから派生したサポートがあるため、複雑な機能も容易に実装が可能です。
FPGAやマイコンを活用した高度な学習方法を紹介
さらに高度な学習を目指す場合は、電子工学にマイコンやFPGAを活用します。
マイコン(マイクロコントローラ)は、電気機器を制御する小さなコンピュータで、半導体製品(IC)の一種になります。
マイコンは家電や自動車に加えて産業機器など、さまざまな電子機器に組み込まれており、実践的な学習が可能です。
マイコンでは、電子工学とプログラミングをベースに設計などを学習できます。
例えば、ARMシリーズのマイコンを使用してマイコンの技術や設計などを学び、最終的には組み込みシステム開発のスキルを高められます。
FPGA(Field Programmable Gate Array)とは、回路の構成をプログラミングできる集積回路(IC)です。
FPGAは最近市場が拡大しており、カスタムデジタル回路の設計スキルを磨けます。
FGPAで利用するHDL(ハードウェア記述用語)を習得すると、高速なデジタル回路や専用回線の設計が可能です。
研究論文や技術書を用いて専門知識を深める方法を解説
電子工学を学ぶコツは、理論と実践を循環的なプロセスとして学ぶ方法が電子工学の理解度をあげる際に効果的です。
そのため、実践的な部分が理解できた後はさらに深い部分の理論、すなわち専門知識や知見が求められます。
専門知識を深めるには、研究論文や技術書からの情報収集も重要です。
研究論文や技術書
電気電子工学分野の学術論文や機関紙を発行するIEEEのドキュメントや各分野の専門書では、最新の技術動向や深い理論的知識を得られます。
IEEEやから発行されている学術誌は、最先端の回路設計技術や半導体技術についての学習が可能です。
学術誌が難しい場合、オープンプラットフォームの論文や記事でも、最新の研究成果から深い部分の知見を増やせます。
いずれにせよ、最新の研究動向を把握し、自身の理解度を高めるのが重要です。
技術書では、アナログ回路設計やデジタル信号処理に加えて無線通信システムや半導体デバイス物理など、特定の分野に焦点を当てた専門書があります。
専門書は、大学より上の大学院レベルの内容が多いため、基礎的な電子工学の知識を十分に身につけた後がおすすめです。
さまざまな企業や研究機関にて、最新の技術や製品に関するオンラインセミナーを開催しています。
日進月歩の電子工学では最新の情報が将来のスタンダードになる場合があるため、日々専門知識や知見を増やしていきましょう。
電子工学の独学を成功に導くための具体的な戦略と習慣化を解説

電子工学の独学を成功させるには、効果的な学習計画の立て方と習慣化が鍵となります。
電子工学は、情報量の多さから一朝一夕で学べる分野ではありません。
長丁場の独学をおこなった経験がない人には、以下のようなポイントで進めていきましょう。
電子工学の独学を成功させるコツ
- 長期的な目標を設定
- 長期間の目標から短期的な目標に分解する
- 学習を習慣化する
- 学習の進捗を可視化する
独学を進めるにあたって障害となるのは、意欲が下がってしまい、途中で止めてしまう点です。
学習の意欲を下げないために、目標設定や習慣化、可視化が重要になります。
電子工学の独学には長期的な目標と短期的な目標から戦略を立てる
目標には、長期的な目標と短期的な目標の2種類があります。
例えば、1年後にArduinoを使ったIoTデバイスを開発できるようになるという長期目標を立てるとしましょう。
次に、長期目標を細分化して、短期目標を設定します。
1年後にArduinoを使ったIoTデバイスの開発をめざした短期目標の例は、以下のとおりです。
短期目標の例
- 1~2ヶ月目:電子回路の基礎を学習
- 3~4ヶ月目:C言語の基礎を学習
- 5~6ヶ月目:Arduinoの基本操作を習得
目標達成には、日々の積み上げと明確な目標設定が必要になります。
目標の設定や達成条件を自分で設定するのが難しい場合は、他の人の真似が近道です。
例えば、境遇が似ている人の学習内容を参考に短期目標を設定します。
加えて、1〜2ヶ月後の進捗具合や自分の成果を参考に、学習計画を修正していきます。
独学の習慣化は生活に組み込むのが一番の近道
人によっては難しい学習の習慣化は、学習を生活の中に組み込むのが良い方法です。
例えば、毎日朝の1時間を学習時間として確保し、毎日5ページ学習するなどの方法があります。
加えて、習慣化アプリなどを活用した学習進捗の可視化も、学習を習慣化する際に便利な方法です。
習慣化アプリの可視化には、以下の利点があります。
習慣化アプリの可視化
- 可視化には達成感による自身のモチベーション維持
- 成長具合が客観的に確認できる
- 努力が可視化され、自信につながる
最終的には生活の中でやる気に頼らず、日々学習できたら目標達成のための準備が完成です。
モチベーションを維持し挫折を防ぐための具体的な方法を紹介
電子工学の勉強で挫折しないためには、勉強のモチベーション維持が求められます。
例えば勉強中に難しい概念に直面した場合、そのまま進むのではなく、基礎を復習して別の角度からのアプローチで理解度を深める方法があります。
複雑な回路が出てきた際は、単純な部分回路に分解して理解する方法や、シミュレーションソフトで動作を視覚化する方法が効果的です。
さらに、日々の学習成果を振り返ると、知識が徐々に定着していきます。
月に一度その月に学んだ内容や、勉強量をまとめるなどの方法で学習を振り返ると、自身の成長を実感できるためおすすめです。
コミュニティとSNSを活用した学習環境の構築方法を解説
最近では、コミュニティやSNSを活用した学習環境の方法があります。
技術者系プラットフォームを活用して電子工学に関する質問をする、ブログで学習内容を公開するなどで、同じ属性の人に知ってもらえます。
電子工学のSNSやコミュニティの大部分は、無料で参加が可能です。
コミュニティ参加により、経験が豊富なエンジニアからアドバイスを得られ、最新の技術トレンド情報がタイムラインに投稿されます。
さらに、オフラインの電子工作サークルなどでは、実際に他の学習者や専門家と交流して知識やスキルの共有が可能です。
ある程度電子工学が理解できた後は、電子工作コンテストのようなイベントへの参加も、スキルアップの良い機会です。
コンテストのようなイベントでは、限られた時間内で作品を完成させる必要があり、さまざまな経験からスキルが身につきます。
加えて、コンテストを通じて学習者や専門家と知り合えるなどの利点があります。
電子工学を独学で勉強するには理論と実践を通して学習し続けるのが大切

本記事では、電子工学を独学で勉強する方法を紹介しました。
電子工学は学習範囲が基礎から応用まで幅広く、理論と実践を繰り返しながら学習していきます。
理論や実践だけでは、理解度を上げるのは難しいかもしれません。
そのため本記事で紹介した方法を組み合わせると、電子工学をより効果的に楽しみながら独学が可能です。
電子工学は理論に加えて実践スキルが必要なため、独学は険しい道のりになります。
しかし、継続的に続けると確実にスキルを向上できます。
電子工学の知識は今後ますます重要性を増す分野のため、ぜひ独学の学習方法を身につけ、キャリアを成長させましょう。